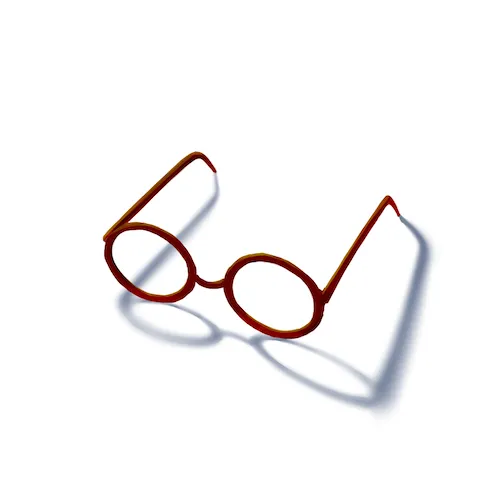Hungry Like the Germ
それは体内の細胞たちにも、秋の終わりと深まりつつある冬の寒さが実感できるようになってきた時期の、ある日のことだった。
ある血管の路地裏に、5人の幼い女の子たちがいた。彼女たちは傷ついた血管や細胞壁の修繕を担当している血小板という細胞たちだった。
彼女たちは今、肺炎球菌、化膿レンサ球菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、ミュータンス菌と、全員が細菌の扮装をしていた。
そして彼女たちは今、全速力で走っていた。
何人かは走りながら自分たちの背後をしきりに振り返っている。なにかに追われているようだった。
「このままじゃ無理!追いつかれるよ!」ミュータンス菌に扮した血小板が走りながら皆にそう叫んだ。
「体力も足の長さも違いすぎるよー!」緑膿菌に扮した血小板が半ベソ状態でそう言った。
「ああもう、どうしてこんなに上手くいかないの…!」
ことの始まりは数日前に遡る。
きっかけは血小板たちが樹上細胞から見せてもらった一枚の写真だった。
「もうずいぶん昔のことなんだけど、以前は体内環境が乱れがちになる冬の始まりにあわせて、こんな行事が行われていたらしいよ」
血小板たちは樹状細胞が差し出した写真を覗き込んだ。セピア色の古ぼけた写真の中には自分たちよりも何世代か前の血小板たちが写っていた。彼女たちは様々な細菌に扮装していて、他の細胞たちからなにかプレゼントのようなものを受け取っていた。
「これは…なにかのお祭り?」
この血小板のグループの副リーダーで、前髪を切りそろえた大人しそうな雰囲気の血小板がそう呟いた。
「これはハロウィンというお祭りで、血小板たちがこの体に害をなす細菌に扮して、この体の細胞たちを訪ねて回り、お菓子を貰うんだ」
樹状細胞がそう説明した。
「お菓子?!お菓子を貰えるの?」
この血小板のグループのリーダーで、髪を後でふたつに束ねた快活そうな雰囲気の血小板が目を輝かせた。
「そう。そして、血小板たちにお菓子をあげられなかった細胞は、血小板たちからなにかいたずらを受けなければならない」
「お菓子を貰えたり、いたずらできたり…なんか楽しそうだね!」
自分たちの知らないお祭りの話を聞いて、盛り上がる血小板たち。
「どうして細菌の格好をするの?」
副リーダーの血小板が、そう疑問を口にした。
「一説によると、体内を回る時に本物の細菌に狙われないように細菌のふりをしていたそうだよ。この写真は僕の先代の樹状細胞が撮ったものでね…正確な起源は僕にもよくわからないんだけど、一種の厄払いとしてこのハロウィンという行事が行われていたみたいだね」
「やくばらい?」
「悪いことが起こらないようにするためにやる、おまじないみたいなものかな。ただ…」
写真をアルバムにしまいながら、樹状細胞はわずかに表情を曇らせる。
「それから体内環境が悪化して、徐々にそういう行事を行う余裕もなくなったからね…このハロウィンももう長い間行われなくなって、すっかり廃れてしまった」
樹状細胞の言う通り、この体の体内環境は長い間深刻な状況に陥っていた。腎臓や膵臓、体内のあらゆる臓器が病に侵され、メンタル面でもうつ病に陥り、ついにはがん細胞まで現れた。
だが、過酷ながんとの戦いを乗り越え、その後の各細胞たちの懸命な働きの甲斐もあって、この体も徐々に立ち直っていった。この体そのものの意識も明らかに変わった。ここ数ヶ月は体内の細胞たちも、とても穏やかな日々を送っていた。
「よし!私たちでそのハロウィンを復活させよう!」
血小板のリーダーがそう宣言した。お?と樹状細胞が興味深そうにその血小板に視線をむけた。
「やろうやろう!今はこの体もだいぶ平和になったし!」
「うん!ただで菓子が貰えるなんて最高!お菓子が貰えなくてもいたずらできるし!」
他の血小板たちも、みな乗り気でそれに賛成した。
そういうわけで、血小板たちはハロウィンの扮装の準備に意気揚々と取り掛かった。誰がどんな細菌に扮装するのか、みんなで話し合いながら衣装を作るのはとても楽しかった。
そして今日。早速血小板たちは細菌に扮して、道を行き交う細胞たちにかたっぱしからお菓子を要求していった。だが…
「わっ?!なに?…え、ハロウィン?…ってなに?」
「うわっ?!あ、なんだ血小板か…え?お菓子?持ってないよ。なんで?」
ほとんどの細胞はハロウィンのことを知らず、お菓子を要求してもただぽかんとした反応が返ってくるだけだった。
「ごめんね…もし知っていたら、なにかしら用意できていたんだけど…」
高齢の細胞の中には、昔行われたハロウィンを覚えている細胞もいたが、突然「お菓子をちょうだい!」と言われて、都合よくお菓子を用意している細胞はいなかった。
しばらく体内を練り歩いていた血小板たちだったが、結局なんの成果も得られず、彼女たちは細菌の扮装のまま、近くにあったベンチに座り込んだ。
「衣装作りに夢中で気づかなかったけど、他の細胞さんたちにもハロウィンのこと、お知らせしておくべきだったね…」
化膿レンサ球菌の扮装をした副リーダーの血小板が呟いた。
「どうしよう…せっかく仮装したけど、もう帰る?」
ミュータンス菌の扮装をした血小板が少し気落ちした様子で言った。
「いやみんな!ハロウィンはお菓子をもらうだけじゃないよ!」
肺炎球菌の格好をした血小板のリーダーがそう叫ぶ。
「樹上細胞さんが言っていたでしょ?『仮装している血小板にお菓子をあげなかった細胞は、血小板からいたずらされる』って!」
実のところ、この血小板たちの最大目標は道ゆく細胞たちからただでお菓子をたくさん貰うことだった。なので、お菓子を貰えなかった場合どういういたずらをするかまでは、今の今まで彼女たちは特に考えていなかったのだった。
「どうせお菓子をもらえる可能性がほとんどないなら、もうこの際、こっちからみんなに積極的にいたずらしてやろうよ!」
「…おぉ!」
元々いたずらが大好きなヤンチャっ子集団であったこの血小板たちは、結局細胞たちからお菓子をもらうことは諦め、人気のない路地裏に潜んでそこを通りかかった細胞たちを驚かすといういたずらに興じ始めたのであった…
「おやおやおやぁ…これはうまそうな細胞だぁ…」
路地裏を通りかかった一般細胞の青年に、早速物陰から不気味な声を作って話しかける血小板のリーダー。
「な…んだ?この声どこから…?」
不意に聞こえた声にぎょっとする一般細胞の青年。
「おりゃ!喰らえぃ!フィブリンッ!」
「ぉわ!なに?!なになに?!」
他の血小板たちが物陰から青年の背後に忍び寄り、フィブリン(※血小板が傷口などを塞ぐ際に用いる血液の凝固に関わるタンパク質。細菌の中にもこのフィブリンを利用するものもいる)を青年に頭からかぶせた。慣れた手つきで青年をフィブリンでグルグル巻きにする血小板たち。
「そして必殺ッ!コアグラーゼッ!!」
「ぐああああーっ?!」
細菌のようにフィブリンに電流のようなエネルギーを流して攻撃…という能力は血小板には備わってない(※仮に備わっていたとしても、やってはいけない)ので、代わりに両手で一般細胞の体をひたすらくすぐりまくる血小板たち。
「こーちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょ!」
「ぎゃあ!はっ!ははははっ…!や…やめて…ほんとやめて!」
くすぐられ、笑いすぎて呼吸が苦しくなっている一般細胞の青年。
「み、みんな…仕事道具をいたずらに使ったら、巨核球先生に怒られるよ…」
唯一いたずらには加わらなかった副リーダーが心配そうに言った。
だが、皆いたずらに熱中していて副リーダーの声が聞こえていないようだった。
「あーっはっはっはっはっ!手も足もでないみたいだね!この無敵攻撃に!」
黄色ブドウ球菌に扮した血小板に至ってはもう完全に細菌になり切っていた。
「だ!誰か!助けーてー!!」
「どうした!!」
その時、誰かの大声が路地裏に響いた。
血小板たちが声のした方に目をやると、路地裏の入り口にひとりの細胞が立っていた。
「お前ら…細菌か?!随分ちっこいが…一般細胞を狙って集団で襲うとは…」
その細胞の姿は、血小板たちからは距離が離れている上に逆光でよく見えなかったが、影のシルエットから少なくとも髪型はツインテールで、腰には剣のような武器を携えていることはわかった。
「お…あ!リーダー…リーダーやばいです…あのひと免疫細胞っぽい…」
「あ、うん。白血球…さん…だね」
「ど、どうしますか…逃げますか…?」
「うん逃げよ、逃げよう…逃げろ!!」
一目散に駆け出す血小板たち。
「待てこらああぁッ!!」
「ぎゃあああーっ!」
物凄い怒気を放ちながら猛然と追いかけてくるツインテールの白血球から、血小板たちは必死に逃げ回った。
そして場面は冒頭へと戻る。
「このままじゃ無理!追いつかれるよ!」
ミュータンス菌に扮した血小板が走りながら皆にそう叫んだ。
「体力も足の長さも違いすぎるよー!」
緑膿菌に扮した血小板が半ベソ状態でそう言った。
「ああもう、どうしてこんなに上手くいかないの…!」
肺炎球菌に扮したリーダーが独りごちた。
「ねえ!ここは仮装を解いて、素直に投降した方が…」
ミュータンス菌に扮した血小板が言う。
「うん!そうだね!そうしよう!」
リーダーが秒でその意見に賛同した。
「でもこの格好で細胞さんを襲ったのは事実だから、どっちにしろこっぴどく怒られるだろうね…」
黄色ブドウ球菌に扮した血小板が少し後悔した様子でそう呟いた。
「やっぱり逃げよう!全力で逃げよう!」
怒られるのは嫌だと、秒で前言を撤回するリーダー。
「みんなこっち!」
その時化膿レンサ球菌に扮した副リーダーが皆の前に先んじて駆け出した。
「みんな私についてきて!」
緑膿菌に扮した血小板が指摘した通り、体格的にも体力的にも劣る血小板たちが白血球の追走から逃げ切るのは無謀であるかのように思われた。
だが、血小板たちは日々の仕事で体内のあらゆる道を知り尽くしていたし、白血球たちが移動に使っている遊走路の構造もそれなりに把握していた。血小板たち自身は遊走能力を持たないが、仕事の際には遊走する白血球にくっついて傷口まで連れて行ってもらうことが度々あったからだ。(※これを白血球-血小板複合体と呼ぶ)
「ねえ!こっちの道は?私たちがギリギリ通れるくらいの狭さだから、あの白血球さんは通れないかも!」
「そっちはダメ!進んだ先に遊走路のハッチがある!」
ツインテールの白血球が自分たちを一網打尽にするために遊走路を使って先回りしてくると予想した血小板の副リーダーは、遊走路の出入り口が少ない道を選んで皆を先導した。結果的にこの副リーダーの作戦は功を奏し、血小板たちはツインテールの白血球の追走からなんとか逃れることに成功したのだった。
「くそ…見失った…」
『こちら白血球1212番…こちら白血球1212番…おーい、1178番。戻ってないの、お前だけだぞー。どこいったー?』
「…こちら白血球1178番。リンパ節に戻る途中で細菌の集団を発見した。奴らを追跡していたんだが…取り逃した」
『ほお…あんたが細菌に遅れを取るとは珍しい』
「いやそれが妙なんだ…やたらちっこい細菌どもで、レセプターにも反応しなかった。逃げ方にも妙に迷いがなかったし…」
『ふーん…ちっこかったということは、細菌の子供だったのかな?その細菌による被害は?』
「今のところはなにも…一般細胞がひとり奴らにたかられてたけど、助けてみたらフィブリンでグルグル巻きにされていただけで、特に怪我はしていなかった」
『まあレセプターにも反応しない、細胞にも怪我を負わせられないような弱っちい雑魚ってことなら、今急いで対処する必要はないんじゃない?一応そいつらのことはこれから勤務に入る87たちに伝えておくからさ。あんたは勤務時間すぎているんだし、もう上がりなよ』
「んー…でも雑魚とはいえ、見つけた細菌を取り逃がしたまま仕事を終えるのはなぁ…」
『あんた、”姐さんは働き過ぎだ。今は人手にも余裕があるんだからちゃんと休め。仲間を信じて仕事を任せるのも大切だぞ”って96にはしょっちゅう言ってるじゃん。そのあんたがオーバーワークしてたら格好つかんぞ?』
「はあ…了解…これから戻るよ…そう言えば姐さんは?」
『今日はもう上がったよー。なんかこの後用事があるみたい』
「どうにか逃げきれたみたいだね…」
「疲れた…」
全速力で体を走り続けた血小板たちはもう息も絶え絶えの状態で地面に座り込んだ。気づいたら彼女たちは体の末端の毛細血管のあたりまで逃げ延びていた。
「リーダー!ここは一旦方針の立て直しを提案します!」
しばらく息を整えた後、ミュータンス菌に扮した血小板がリーダーにそう進言した。
「そうだね…お菓子を要求するにしろ、いたずらを仕掛けるにしろ、今後は闇雲に声をかけるんじゃなくて、ターゲットを絞っていこう!」
そう言って立ち上がるリーダー。
「え…まだ続けるの?」
副リーダーはもうあまり乗り気ではない様子だった。
「だってせっかく何日もかけて衣装も用意したんだよ?!ここまできたらなにかひとつ成果を得られるまでは帰れないよ!大丈夫!今後は、細菌に扮した血小板に危害を加えようとしてこない、優しくてお菓子を恵んでくれそうな細胞だけを狙えば!」
「…そんな細胞いるかな?」
緑膿菌に扮した血小板が首を傾げる。
「マクロファージさんたちは?おっとりしてて優しいし…」
黄色ブドウ球菌に扮した血小板が提案した。
「でもマクロファージさんたちも免疫細胞だし…もしこれが仮装だと気づいてもらえなかったら、またさっきみたいに駆除されそうになるかも…」
ミュータンスに扮した血小板が慄く。
「うむ…免疫系の細胞さんたちは一旦候補から外そうか…」
腕を組んで考え込むリーダー。
「としたら…狙うのは非免疫系の細胞を中心に…」
「あ!あのひとはどう?」
黄色ブドウ球菌に扮した血小板が声を上げた。
「ん?どのひと?」
「あの、ほら!あそこで酸素を運んでいる赤血球さん!」
その血小板が指差した方を見ると、一人の若い赤血球が酸素の入った箱を積んだカートを押しながら、こちらに向かってくるのが見えた。黒髪に赤いほっぺが印象的だった。
「なるほど…赤血球さんならグルコースのお菓子とか持ってるかも…!」
赤血球は成熟の段階でミトコンドリアを捨て去るため、白血球や一般細胞などとは違いグルコース(ブドウ糖)のみをエネルギー源としている。なので他の細胞たちに比べれば、甘い食べ物を持っている可能性は確かに高いように思われた。
「それにあのお兄ちゃんなら頼み込めばなんとかいけそう!あのお兄ちゃん、なんか押しに弱そう…優しそうだし!」
黄色ブドウ球菌に扮した血小板がそう言った。
「あ!あのお兄ちゃんは…」
その時リーダーが何かに気づいた。
「おっと…ここの毛細血管も道が狭くなってるな…」
そう呟きながら、カートから酸素の入った箱を持ち上げる赤血球。
「しーっ…静かに…静かに…」
その前方の毛細血管の曲がり角の死角で息を潜める血小板たち。
「寒い時期はこれだからな…」
「…せーの、ばっ!!!」
赤血球が近づいてきたタイミングを見計らい、血小板たちは一斉に赤血球の目の前に飛び出した。
「わわっ!?何だー!?え…何だ?!細菌!?の子供??」
驚いて、危うく抱えている酸素を落としそうになる赤血球。
「きゃはは!また引っかかったー!」
「あれ⁈その声は…⁈」
嬉しそうにはしゃぐ声に聞き覚えがあることに気づく赤血球。
「久しぶり!赤血球のお兄ちゃん!」
血小板のリーダーはそう言うと、肺炎球菌の頭の被り物を取った。
半年ほど前までは、血小板のリーダーと副リーダーはまだ赤色骨髄から出たことがない未成熟の血小板だった。その彼女たちに鼻腔の出血を止めるための出動要請が来たことがあった。当時はまだ体内の復興が始まったばかりで、各細胞たちの人手不足もまだ解消されていなかったのだ。
初めて赤色骨髄を離れて仕事をすることへの恐怖に怯える自分たちを励まし、その初仕事に終始付き添ってくれたのが、この赤血球の青年だった。
「しばらくだったね。元気そうでなによりだよ」
赤血球が血小板のリーダーと副リーダーに笑顔を向けた。
「うん!あれから血小板としてバリバリ働いているよ!お兄ちゃんのおかげでね!」
元気よくそう答えるリーダー。その後で副リーダーがぺこりと頭を下げた。
「いや…そんな…」
赤血球は照れくさそうに赤い頬をぽりぽりと掻いた。
「ところでみんな、今日はそんな格好でなにをしているの?」
「これはハロウィンだよ!」
「ハロウィン?」
「そう!この体の…む…無情…ぞんざい…?」
「…無病息災?」
「そう!むびょうそくさいを願って、この体の細胞たちみんなが細菌たちの格好をした血小板たちにお菓子を恵んだよ!」
「…よくわからないけど…この体ではそういうイベントがあるんだね…」
言葉通りあまりよくわかっていない様子で赤血球がそう言った。
「あ、そうか。お兄ちゃんは元々別の体から来たんだっけ?お兄ちゃんの体では、そういうお祭りはなかったの?」
「うーん…聞いたことないなぁ…僕がいた頃のあの体は、体内環境がほとんどブラックな状態だったから、そういう行事があったとしても実施する余裕がなかったのかもしれないけど…」
「うーん…色々苦労が多いのはこの体だけじゃないんだねぇ…」
「…ちなみに今はなにかお菓子とか持ってます?」
ミュータンス菌に扮した血小板が遠慮がちに尋ねた。
「いや、残念だけど…今はまだ仕事中だし…」
「そっかぁ…」
がっかりした様子でリーダーが項垂れた。
赤血球はしばらく考え、そして言った。
「それならさ、仕事が終わっている赤血球の家に行ってみたらどうかな?」
「ん?」リーダーが顔を上げた。
「血球の人手不足もだいぶ解消されてきて、今は赤血球の勤務シフトもかなり余裕があるんだ。この時間帯なら…勤務時間外の赤血球が何人か家で休んでいるはずだよ。赤血球の家ならグルコース製の甘い食べ物がたくさんあると思うし」
「なるほど!」
黄色ブドウ球菌に扮した血小板が頷いた。
「早速行ってみるよ!ありがとうお兄ちゃん!」
リーダーが赤血球にお礼を言った。
「ふーん…なるほど、そういうことね」
そんな血小板たちと赤血球のやりとりを、ひとりの白血球が物陰からこっそりと聞いていた。
「それじゃあまた!お兄ちゃん、お仕事頑張ってね!」
「うん。君たちも気をつけて」
血小板たちと赤血球が別れたのを見届けると、その白血球は八重歯を覗かせてニヤリと微笑む。そして後ろで束ねた紫色の髪を翻し、どこかへと立ち去って行った。
「このマンションだね」
道中、免疫細胞に出くわさないように気をつけながら、血小板たちはなんとか赤血球たちが住むマンションへとたどり着いた。時刻はもう夕方になっていた。
「どの部屋にする?」
「窓から明かりが見える部屋なら、その部屋には誰かがいるってことだよね…」
そう会話しながらアパートの通路を歩いて行く血小板たち。
しばらくして、血小板のひとりがあることに気づいた。
「ねぇ…なんか甘くていい匂いがしない?」
「ん!確かに!」
「こっちの方かな?」
血小板たちは甘い匂いの源を探って通路を歩いて行く。
「あ!見てこれ!」
緑膿菌に扮している血小板がある部屋の前で立ち止まって、その部屋の玄関のドアを指差した。
見るとその部屋の玄関のドアには張り紙が貼ってあり、こう書かれていた。
"ハロウィンを楽しんでいる良い子たちへ!甘いものをいっぱい用意しているよー!🤗✨ぜひ立ち寄ってね!😋❤️"
「おぉ…!」
「これは…!」
「甘い匂いもこの部屋から来ている気がする!」
にわかに興奮する血小板たち。だが…
「罠だ…これは罠だ!」
副リーダーの血小板が張り紙を指差しながら、近所迷惑にならない程度の声量でそう叫んだ。
「え?」
「なに?」
「急にどうしたの?」
他の血小板たちは皆一様にぽかんとした表情で副リーダーを見ている。
「ぜ、絶対おかしいよ!甘い匂いを辿った先の部屋のドアにこんな張り紙があるなんて!こんな、あからさまに…今までハロウィンを知っていた細胞なんてほとんどいなかったのに…!」
そう言って副リーダーは疑念に満ちた表情で部屋のドアを凝視し、後ずさった。
「えー?でも一般細胞のおばちゃんはお菓子は持ってなかったけどハロウィン自体は知ってたよ?」
リーダーがあっけらかんとそう言った。
「この赤血球さんも昔からハロウィンを知ってるおじちゃんで、いつかハロウィンに訪ねてくる血小板たちのために、毎年お菓子を用意していたのかも…」
「そ、そんな都合の良い話があるわけ…ていうかこの文体…どう考えてもおじさんじゃ…」
「とりあえず聞いてみようよ」
血小板のひとりがそう言うと、躊躇なくその部屋の玄関のチャイムをピンポーンと鳴らした。
「なああ!ちょっちょちょっと!」
もはや声量など気にせずに副リーダーが叫んだ。
「副リーダーちゃん、そんなに騒いだら近所迷惑だよ?」
別の血小板が副リーダーの肩にポンと手を乗せ、嗜める。
「もう!どうしてみんなもうちょっと考えてくれないのー!?」
少し半泣き状態になっている副リーダー。
…ガチャリ。
玄関のドアが開いた。そして…
「うぇええッ!?」
「…む?」
玄関のドアを開けて現れたのは赤血球ではなく、白血球だった。
その白血球は白銀のロングヘアを持つ妙齢の女性で、右目は長い前髪によって隠れていた。白血球の帽子は被っていなかったが、白い白血球の仕事着には小さい赤色の染みが所々についていた。凛々しい雰囲気を持つ美人だったが、それゆえかどこかおいそれとは近づきがたい雰囲気も持っていた。
まったく予想外の展開に硬直する血小板たち。
「……」
当の白血球は無表情のまま何も言わずに、白銀の髪の間からのぞく左目で血小板たちをじっと見ていた。
硬直している血小板たちの中で、まず副リーダーが我に返った。
「あ…あの!私たちは細菌じゃありません!血小板です!」
白血球に本物の細菌と誤解されて駆除される可能性を真っ先に排除しなければならないと思ったのか、副リーダーはそう叫んだ。そして自分が被っている化膿レンサ球菌の頭を脱ぐ。
「…そのようだな」
白血球は静かにそう言った。
「ほ…本当に罠だったなんて…」
「こんな巧妙な罠を…」
他の血小板たちも観念した様子で、次々と細菌の頭を脱いでいく。
「あ…あれ?お姉さんは…」
その時、副リーダーは目の前にいる白血球と以前会っていることに気がついた。
「あ…お姉ちゃん?」
肺炎球菌の被り物を取ったリーダーもそれに気づいたようだった。
「ん…お前たちか。ひさしぶりだな」
白血球が血小板のリーダーと副リーダーを見てそう言った。
「あれ…ふたりとも、この白血球さんのこと知ってるの?」
血小板のひとりがリーダーと副リーダーにそう尋ねる。
「あ、うん。私たちが未成熟の時に赤色骨髄で会ってて…」
副リーダーが言った。
「へぇ…」
「その時は肩車して一緒に遊んでもらったりしてたんだ!私たちの初仕事の時も一緒に付き添って来てくれたし…このお姉ちゃん、ちょっと怖そうに見えるけど、本当はとっても優しいお姉ちゃんなんだよ!」
リーダーがそう付け加えた。
「へぇ…」
「ッ!…ンん…」
白血球は表情を変えないまま、軽く咳払いした。
ひょっとして照れてるのかな?とそれを見た副リーダーは思った。
「お前たち、なにか用があって訪ねて来たんじゃないのか?」
白血球がそう血小板たちに尋ねた。
「私たち、そのドアの張り紙を見て…」
血小板のひとりがドアの張り紙を指差した。
「張り紙?」
白血球は首を傾げた。そして玄関のドアに貼ってある張り紙の存在に気づく。
「…なんだこれは?私が来た時には、こんなものは貼っていなかったぞ…」
そう言いながら、白血球はドアから張り紙を剥がした。
「え?それ、お姉ちゃんが貼ったんじゃないの?」
「違う。私がこの部屋に来たのは2時間ほど前だが…いや待てよ…この筆跡は…」
張り紙の文章を読んだ白血球がなにかに気づいた。
「…これに書かれているハロウィンというのはなんのことだ?」
白血球がそう尋ねた。血小板のリーダーがハロウィンについて簡単に白血球に説明した。
「ほう…この体にはそういう行事があったのだな」
「お姉ちゃんも元々別の体にいたんだっけね」
「ああ…恐らくこの貼り紙は私がこの部屋にきた後に他の誰かがこの部屋のドアにこっそり貼り付けたものだろう…まあ誰がやったのかは察しがついているが…」
やれやれと白血球は嘆息すると、改めて血小板たちに向き直った。
「さて、事情はわかったが、血小板たちがそんな格好で体内をうろついていたのは感心しないな。勘違いした免疫細胞に攻撃されても文句は言えんぞ?」
「う…」
少し前にツインテールの白血球に追いかけ回されたことを思い出し、リーダーが俯く。
「まあ、そのハロウィンという祭りをすること自体は反対しない。ただその祭りは長いこと行われなくなっていて、存在を知っている細胞も少なくなっていたのだろう?祭りを安全に楽しむためにも、他の細胞たちにも事前に情報を共有して、理解を得ておくべきだったな」
「それは…はい…」
白血球の正論に、副リーダーも項垂れる。
「…まあいい、とりあえず今日はもうまっすぐ帰りなさい。一応この後私から免疫細胞各位に連絡をしておこう。仮装しているお前たちを間違えて攻撃しないように、とな。来年からはちゃんと事前連絡をしておくんだぞ」
「あ、はい!ありがとう!ございます!」
一斉にお礼を言う血小板たち。思いがけず白血球に対面してしまった時はどうなるかと思ったが、今回は穏便に済みそうだった。
「あ、あの…ところでお姉ちゃん」
少し緊張がほぐれてきた様子の血小板のひとりが、なにかを思い出したかのような表情で口を開いた。
「ん?なんだ?」
「お姉ちゃんはどうして赤血球さんのお家にいるんですか?」
「え…え?」
相変わらず無表情を崩さない白血球だったが、声が若干上ずっていた。
「っ…それは…」
目線を若干泳がせながら、白血球は言い淀む。
「このお部屋に住んでいる赤血球さんと友達なんじゃない?それで遊びに来ているとか」
血小板のひとりが言った。
「そうなの?」
血小板のリーダーが白血球に尋ねた。内心ではリーダーは「でも、このお姉ちゃんはなんというか"仕事一筋"なイメージで、友達の家に遊びに行くようなイメージではないなぁ」と思っていたが、口には出さなかった。
「友達…というか…あいつとは…いや、この家の主とは…その…仕事上で付き合いがあって…」
先ほどの毅然とした態度が徐々に崩れてきている白血球。
「仕事のことで、ここに住んでいる赤血球さんになにか相談しにきたとか?」
血小板のひとりがそう聞いた。
「え?…あ!うん…そんな感じだ…うん」
口ではそう肯定したものの、相変わらず白血球の目線は泳いでいる。
「あ!じゃあ!その赤血球さんになにかお菓子がないか聞いてみてくれませんか?」
今度は別の血小板が白血球にそう尋ねた。
「え?」
白血球の声がさらに上ずった。
「この部屋に住んでいる赤血球さん!今いるんですよね?」
「そうだ、そもそも私たち、なにか美味しそうな匂いにつられてここに来たんだし」
別の血小板が思い出したように言う。
「そっか、この部屋に住んでいる赤血球さんが料理する匂いだったんだね」
当初の目的が果たせそうだ、と盛り上がる血小板たち。
「いや…いない。あいつは今日は朝から仕事で…」
言いにくそうにそう言う白血球。
「え?いないの?」
キョトンとした表情になる血小板のリーダー。
「あ…うん。いや…あいつは今日は夕方までの勤務だから、そろそろ帰ってくるとは思うが…」
「んん?ちょっと待って…じゃあ今この部屋にいるのはお姉ちゃんだけってこと?」
頭に手を当て、考え込むリーダー。
「ん…そう…だな…」
「お姉ちゃん、さっき"自分は2時間ほど前にこの部屋に来た"って言ってたよね?でもこの部屋の赤血球さんは今日は朝から仕事をしている…」
「……そうだが」
「部屋の主がいないのに…お姉ちゃんはどうやってこの部屋に入ったの?」
「…エ?」
白血球の声が、さらに1オクターブ上がった。
「確かに…」
「おかしいね…」
リーダーと同じく他の血小板たちも不審がる。
「赤血球さんがいない間に無断で勝手に入ったってこと?」
「え、それって不法侵入なんじゃ…?」
「まさか白血球の遊走路を使って…?」
どんどんと悪い方向に想像を膨らませる血小板たち。
「いや待て!違う違う違う!この部屋にはちゃんと合法的に入った!ほら!この部屋の合鍵で!」
慌てた白血球は、ベルトのカラビナを外し、そこに付けられた鍵を掲げた。
「合鍵?」
血小板たちが白血球の持つ鍵に注目する。
「そうだ!この部屋の主からもらった合鍵だ!断じて不届きな手段で入ったわけではない!」
最初の毅然とした態度をいくらか取り戻し、堂々とそう宣言する白血球。
だが、血小板たちは依然釈然としない表情だった。「仕事仲間というだけで自宅の合鍵を渡すものかな?」という疑問が血小板たち全員の頭の中に共通で浮かんでいた。
「白血球さん」
その時、血小板たちの背後から声が聞こえた。
「あ…おかえり…」
白血球が少し気の抜けた様子で声の主にそう声をかけた。
「ただいま…です……どうかしたんですか?彼女たちは?」
血小板たちは一斉に声の主の方へ顔を向けた。
そこにはひとりの赤血球が立っていた。深い赤色のくせ毛の、メガネをかけた青年だった。赤血球にしてはかなり逞しい体つきで、背も白血球よりほんの少し高いようだったが、不思議と威圧感はなかった。声といい顔つきといい、とても穏やかで優しい雰囲気の青年だった。
(あ!この赤血球のお兄ちゃんは…)
血小板のリーダーはこの赤血球を見て、不意に思い出した。
それは半年前、自分が鼻腔で血小板としての初仕事を無事に終えた後に目撃した、ある光景のことだった。
「…ただいま白血球さん…」
「…おかえり…赤血球…!」
どんな時でも強くて冷静でカッコよくて、頼り甲斐のある白血球のお姉ちゃん。
そのお姉ちゃんがその時に初めて見せた涙を、血小板のリーダーは今でも覚えていた。
(そうか…このふたりは…)
「おふたりは恋人同士だったんですね」
リーダーと同じく半年前の光景を覚えていた副リーダーがそう呟いた。
その場にいた全員が一斉に副リーダーを見た。唯一白血球だけはその副リーダーの言葉を聞いた瞬間に、顔を真っ赤にして固まった。
「え…あれ?今私…声に出てた?」
皆の視線に我に返った様子でたじろぐ副リーダー。
無意識でつい口に出てしまったらしい。
「それじゃあみんな、気をつけて帰ってね」
赤血球が血小板たちにそう声をかけた。
「はーい!」
血小板たちが一斉に、元気よく答えた。彼女たちの手にはグルコース製の甘いお菓子の包みがひとつずつ握られていた。手ぶらで帰らせるのもなんだからと、白血球と赤血球が自宅にあるお菓子をいくつか分けてくれたのだった。
「お姉ちゃん!と、お兄ちゃん!」
血小板のリーダーが前に進み出た。
「色々とありがとう!また来年も来るから!その時もお菓子よろしくね!」
「ああ、覚えておくよ」
苦笑しながら白血球が答える。
「ふたりともお幸せに!」
「……」
無言で顔を伏せる白血球。まだ少し顔が赤かった。
「あ…うん」
赤血球も照れてはにかんだ。
白血球と赤血球のカップルに手を振りながら血小板たちは帰って行った。
「結局、今回の私たちのハロウィンは成功だったのかな?」
副リーダーがリーダーにやや疲れた様子で尋ねた。
「うーん…成功ってことで良いんじゃない?いたずらもできたし、お菓子も手に入れたし…それにお菓子以外にも甘いものにもあやかれたしね!」
「…それって、あのふたりのこと?」
「ふふ!この体の平和が続いて、あのふたりみたいに幸せに暮らす細胞たちが増えていけば、来年のハロウィンはもっとずっと楽しくできるよ!きっとね!」
「……」
「だから、明日からも私たちは自分たちの仕事をがんばろう!」
「…そうだね!」
「…やれやれ、思わぬ珍客だったな…」
「…ところで白血球さん」
「なんだ?」
「帰ってくる途中で、美味しそうな匂いがするなぁと思ったんですが…」
「……」
「ひょっとして夕食作ってくれたんですか?」
「…今日は仕事が早く片付いたからな」
「…だとしても、お疲れだったでしょうに」
「お前だっていつも食事を用意してくれているだろ…だが、いつもお前に作ってもらいっぱなしっていうのは…性に合わない」
「……」
「こういうことは対等にやるべきだ…パートナーなんだからな…」
「……服、少し汚れてますよ?家にあるエプロン、使わなかったんですか?」
「いや、あれはお前のエプロンだし…汚したら悪いと思って」
「はは、エプロンは汚れるものですよ。汚れたら洗えば良いんです。今度からは使ってください」
「……」
「僕らはパートナーですからね」
「…わかった」
(おまけ)
血小板たちが帰り、白血球と赤血球が自分たちの部屋に入った後、マンションの通路の奥の影から紫色の髪の白血球と、黒髪で赤いほっぺの赤血球が顔を覗かせた。
「計画通り…」
「87さん…87さん顔怖いです…完全犯罪を成し遂げた犯罪者みたいな顔になってますよ…」
「ねえ見た?あれ見た?!」
「…急にこんなところに連れてきて…僕配達の途中だったんですけど」
「ああいうのが見たかったんだよー!なんか最近はこっちがからかってもすまして躱されるようになっちゃってさー!」
「はあ…」
「だから血小板ちゃんたちならあの純真無垢な好奇心で堅物な96にも踏み込んでくれると思ってさー!いやー狙い通りだったわー!見た?!あの血小板ちゃんに突っ込まれて慌てる96の顔!いやー最高ですなー!!」
「…それであんな張り紙を先輩の部屋のドアに貼ったんですね…」
「どう?なかなかの策士でしょー?」
「まあ…96さんが今日先輩の部屋で料理をすることも知っていたんですか?」
「いやいや、それは本当にただの偶然だよ。96が今日仕事のあと53くんの家に行くんだろうなーとは思ってだけど。まあおかげで血小板ちゃんたちもまっすぐあの部屋に向かったわけだし、運もこの私に味方したってことだね!それにしてもあの仕事一筋だった96が53くんのために料理とは…いやー愛だねー!」
「はあ…」
「あーあ!あのふたりもいい加減付き合ってること公にすればいいのにねぇ…ああやって休日が重なった日は一緒に過ごしているんだからさ!どうせ親しい私たちはすでに知っているんだし…」
「……」
「…あの…87さん」
「んー?」
「…僕らもそろそろ、一緒に暮らしませんか…?…なんて…」
「あーうん…え?」